【校長室より】ニュースレター「多摩の風」vol.18
更新日時:2024年7月20日
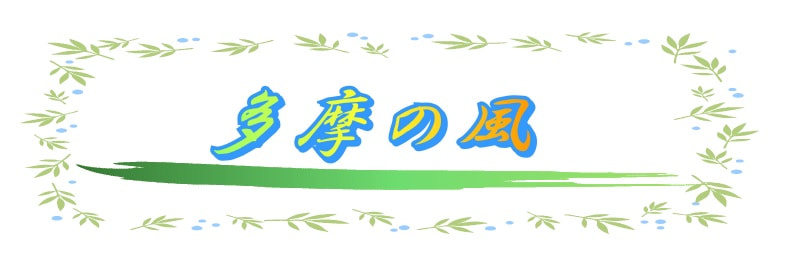
ニュースレター「多摩の風」とは
本校の多彩な教育活動とその魅力を皆さんに紹介したいと思い、整理・編集したのがニュースレター「多摩の風」です。生徒には紙で配布しておりましたが、校内外問わずご好評をいただいていたので、今年度からはHPでもご紹介する運びとなりました。ぜひ、ご覧ください。(一部内容につきましては、学校生活ブログでも紹介しております。)
2024年3月7日、8日、28日の3日間、つまたま保育クラブで唐木田児童館を訪問しました。
生徒達は小さい子ども達との触れあいはもちろんのこと、来館していたママ達との交流も楽しめた様子です。児童館の職員さんから事前にご指導頂いた手遊び歌を披露したり、子ども達と一緒に遊んだりと、楽しい時間を過ごすことが出来ました。この場を借りて、子ども達、保護者の皆様、唐木田児童館の職員の皆様へ感謝申し上げます。
今回は、唐木田児童館に伺って手遊びを披露したり一緒に遊んだりしました。当日、子どもたちと遊ぶ前に児童館で働いている方に手遊びを教えていただき、1歳から5歳の子どもたちに教えて頂いた手遊びや事前に自分たちで考えて用意した手遊びを披露したところ、とても楽しそうに真似をして一緒に遊んでくれました。また、ボール遊びやおままごとなどを通じて子どもたちと接する中で改めて、可愛さや保育の楽しさを感じました。その他にも、保護者の方とお話する機会もあり、貴重な体験をする事が出来ました。今回の経験を活かしこれからも保育クラブとして活動していきたいです。
児童館訪問(つまたま保育クラブ)

つまたま保育クラブとは、昨年度から始まった高校生のボランティア団体で、「小さい子どもと遊ぶのが好き!」「将来保育士になりたい!」といった生徒達が、近隣の未就学児を学校に招いて「つまたまあそびひろば」を開催しています。今回は初めての試みとして、日頃あそびひろば開催の際にお世話になっている唐木田児童館へ「出張つまたまあそびひろば」としてお邪魔させて頂くことになりました。
今年度もつまたま保育クラブは地域の方々と連携しながら、多摩に住む老若男女皆様に愛される学校にしていけるよう、幅広い年齢の方々との触れあいを通して成長していきたいと思います。
以下は、今回の児童館訪問に参加した高校3年生の感想です。
高校3年生 感想
〈第1日〉
中1 オリエンテーション旅行

中学1年生は、4月20日(土)から22日(月)にかけての2泊3日の行程で、河口湖畔でのオリエンテーション旅行に出かけました。この旅行は、学祖大妻コタカ先生の教育理念について学ぶこと、クラス・学年の親睦を深めること、規律ある集団生活を通じ、大妻多摩生として学校生活を送っていくうえで大切な心構えを共有することなどを目的としています。
初日は、ホテルで昼食を済ませたあと、河口湖畔のシッコゴ公園でチームビルディングのプログラムに取り組みました。シッコゴ公園はプログラムの進行を担当してくださったのはNPO法人「富士山ネイチャークラブ」のみなさんです。第1部は、入学してからまだ話したことがない人と挨拶をかわす挨拶ゲームや、富士山に関するクイズ合戦を行いました。第2部は原始人になったつもりで取り組むアクティビティ中心のプログラムでした。
パチンコ、やり投げ、丸太きりといった体を使うゲームや、8種類の植物の中から食べられるものを選び出すクイズなどを、チームで得点を競い合いながら楽しみました。実は、これらのプログラムには「チームのメンバーと協力し合う力を養う」ことだけでなく、「知識・体力・感性を磨く」という隠されたテーマもありました。担当の方から、これからの時代をよりよく生きていくためにはとくに感性を磨いてほしい、というお話がありました。
富士山や河口湖をゆったり眺められるのどかな公園で、仲間との親睦を深められた楽しい1日となりました。
〈第2日〉
午前中の最初のプログラムは、富士山ネイチャークラブの方による講話でした。富士山が今日の美しい姿になるまでのプロセスや、富士山に見られる動植物、富士山が「水の山」とも呼ばれる理由などを、クイズを交えながら楽しく学びました。
続いて熊谷校長から学祖大妻コタカ先生についてのお話がありました。コタカ先生は18歳のときに親の反対を振り切って広島の実家を飛び出し、単身東京に出てきました。やがて小さな裁縫塾を開き、それを今日のような大妻学院にまで発展させたお話を聞いて、生徒はコタカ先生のひたむきな生き方に感銘を受けたことと思います。
午後は1・2組、3・4組に分かれてSDGsボードゲーム、樹海ハイキングを楽しみました。
班ごとに得点を競い合いつつ、個人の得点も競うというSDGsボードゲームでは、自ら必勝法を編み出す人、班のみんなと協力して優勝しようと作戦を立てる人、カードを丁寧に読みながら現代社会の問題点に目を向ける人、それぞれが多様な楽しみ方を見つけ、一生懸命に取り組んでいました。
樹海ハイキングでは、富士山ネイチャークラブの方にガイドをしていただき、樹海の動植物などについて興味深いお話をたくさんしていただきました。また、溶岩の上に生える木々を見ながらキノコに触ってみたり、鳥の歌声に耳をすませたりして、自然の雄大さを五感全てで感じました。バスに戻った生徒たちは「東京より空気がおいしかった~」と満足げな顔をしていました。
盛りだくさんの1日でしたが、みんな疲れた様子も見せず、たくさんのことを感じ、学び取ることができた1日になったことと思います。
〈第3日〉
最終日のプログラムはクラスミーティングと「富士山世界遺産センター」の見学です。
クラスミーティングでは、どんな大人になりたいか、そして、なりたい自分になるために、今後学習面や生活面などおいてどのようなことに取り組んでいきたいかについて考えてもらいました。また、このオリエンテーション旅行で心に残っていることや、この旅行を通して自分が成長できたと思えることについて、グループで発表し合いました。
富士山世界遺産センターでは10名ほどの班に分かれ、綺麗な館内をガイドさんの案内のもと、ゆっくり見学していきました。前日までは富士山を自然科学の観点から学ぶことが多かったのですが、この施設は富士山を信仰の対象かつ芸術の源泉という視点から捉えて解説しています。生徒はガイドさんのお話を聞きながらいろいろな展示物を見て、富士山が世界“文化遺産”であるということがよく理解できたのではないでしょうか。
時間を守ること、しっかり挨拶をすることといった集団生活のルールやマナーを学びながら、クラスや学年の仲間と親睦を深め、たくさんの楽しい知的な刺激も受けられた充実の3日間になったことと思います。
大きな動きにやがてつながっていくことになると信じたいです。
高3のみんな、大妻多摩の魅力の一つである高三ダンスを135人全員で無事に伝統を引き継ぐことができ、良い思い出となりました。6年間の思いが詰まったダンスを踊るために色んなところで努力してくれたダンス係のみんな、お疲れ様!そして、ありがとう!
体育祭(閉会の辞)

みなさん、体育祭お疲れ様でした!体育祭は楽しめましたか?第37回の体育祭が皆さんにとって素敵な思い出の1つになっていれば幸いです。
無事に体育祭を開催するために尽力してくださった橋口先生、金川先生、中浴先生をはじめとする諸先生方、そしてお忙しい中お越しくださいました保護者の皆様、本当にありがとうございました。
中学1年生から高校2年生のみなさん、練習中に意見がぶつかり、うまくいかなかったこともあったと思いますが、その経験を通じて団結力が強まったことでしょう。これからも学年の仲間を大切にし、さらに素晴らしい体育祭を来年度以降も作り上げていってください。
また、総務をはじめとする体育委員のみんな、最初の委員会では失敗ばかりで多くの迷惑をかけましたが、それでもみんながここまでついてきてくれたおかげで体育祭を成功させることができました。本当にありがとう!
大妻多摩中学高等学校で体育委員、総務を務めた6年間は私にとってかけがえのない思い出になりました。皆さんにとっても今年の体育祭が同じような思い出になっていれば幸いです。
以上をもちまして、第37回体育祭を終了致します。
ごきげんよう。
まずはライオンバスに全員で乗車して、ライオンがエサを食べる様子を間近で観察し、大興奮。
その後、皆思い思いの方向に分かれ、放飼場の動物の行動観察をはじめました。30分間ほどじっくり行動を観察しつつ、記録しつつ、という作業です。時間があっというまに過ぎていきました。
引率者の筆者は、あの広大な多摩動物公園を高速で歩きながら各生徒の様子を見つつ、動物に挨拶をしつつ過ごしました。いくつか行っている野外実習のうち、一番腓腹筋が筋肉痛になるのは実はこの実習です。途中、野生の痕跡を見つけることもあり、なんだかちょっと皮肉を感じる場面もありました。が、こちらも存分に動物公園を楽しめました。1年に1回の役得です。
多摩動物公園実習(高3生物)
去る5月29日、毎年恒例、高3生物履修者と共に多摩動物公園へ行ってきました。
これは授業の一貫で動物行動観察実習を行うためです。今年度は授業の配置上、高3の自由選択生物を履修している人を授業の一環として引率しましたが、当日午後に授業が無く空いている生徒(自由選択を取っていない生物履修者)も数名「多摩動物公園で観察したい!!」ということで一緒に行きました。
前日までの嵐が嘘のように快晴で、汗だくになるほどでした。

授業が終わる頃に再集合し、無事を確認してからは自由行動になりました。皆塾などに急いで出るかと思いきや、見たり無い!とのことでまた園内の方々に散っていきました。昆虫館に走って行ったグループもあれば、ニホンザルの猿山に帰る・・・ではなくて観察を続けに行くグループもあり、生物選択者のいきもの愛をひしひしと感じました。今年も無事に楽しく実施できたことにホッとしています。
体育祭翌日の6月9日に、ESS同好会の高校1年生6名が、本校として初めて模擬国連の会議に参加しました。模擬国連とは、生徒たちが国連会議の参加者たち、つまり各国の大使や議長になって、実際の国連と同じ会議方式と流れで国際課題を議論し、解決案を出していく活動です。
1994年のルワンダでは、民族間の対立による大量虐殺が起きていました。「国連の失敗」と非難されるルワンダ虐殺に真剣に向き合い、実際に国連が下した決定よりも建設的な決議案を各国と協力しながら作成し、決議として採択することが、今会議のゴールです。
本校の生徒たちは「南アフリカ大使」と「韓国大使」の役割を与えられました。自分たちが生まれるよりも前の世界情勢を調べたうえで、ルワンダ情勢に対する国のスタンスを決め、緊張して会議当日を迎えました。
模擬国連(ESS同好会)

今回の会議は大妻中高と渋谷教育学園渋谷が運営し、千代田区の大妻女子大学で開催されました。合計38校、総勢500名以上の中高生が参加しました。テーマは「ルワンダ情勢」で、1994年4月20日が会議日として設定された「歴史会議」でした。
参加者多数のため、会議は5つの議場に分かれて行われました。南アフリカチームは、公式討議や文書作成が英語で行われる「一般議場」に、韓国チームは会議が日本語で行われる「日本語議場」に参加しました。
「非公式会議」という、各国が自由に交渉できる時間になると、「先進国」や「アフリカ諸国」、「アジア諸国」など、スタンスが一致している国同士で集まります。さらに、「ルワンダの状況を『虐殺』と形容するか」「どのような支援をいつまで行うか」など、条文の細かい内容も合わせていきます。交渉を経て複数の決議案が提出されると、最終的には全ての参加国がそれぞれの決議案に投票し、過半数の国が賛成したものが国連決議として採択されます。それぞれの議場で、協力しあう国や、最終的に採択された決議の内容が違い、興味深かったです。
初出場だった本校のチームは、非公式会議でなかなか発言できませんでした。会議終了後に生徒たちに感想を聞いてみると、「自分たちの国の意見を問われたときしか発言できませんでした」、「他国の大使の頭の回転の速さに圧倒されました」、「自分たちの国が譲れないラインをもっとはっきりと決める必要があると思いました」など、反省も多かったですが、「次回は事前に自国なりの決議案まで考えたいです」、「小人数で交渉したときは、積極的に質問したり、意見を言ったりすることができました」、「楽しかったです! 他国の話を聞くのも面白かった」など、前向きな意見も多かったです。そして、生徒たち6名ともが「8月の会議にも絶対参加します!」と決意を新たにしていました。
次回の会議で更に成長した「モギコッカー」としての生徒たちの活躍が楽しみです。
6月18日(火)、ステファン・ハウクル・ヨハネソン駐日アイスランド大使が来校されました。本校では、2022年度にセルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ大使、2023年度にコルクット・ギュンゲン駐日トルコ大使に講演していただきました。駐日大使をお呼びするのは今回で3度目になります。
多摩市は東京オリンピック開催時、アイスランド共和国のホストタウンとなり、その後も「友好都市」として交流を継続しています。6月17日のアイスランド独立記念日にちなみ、多摩市内で様々な関連イベントが開催されました。大使が多摩市内にある学校で講演を希望され、今回は先方よりお話をいただきました。講演会には生徒、保護者、教員を合わせて100名以上が参加し、大変盛況でした
「火と氷の国」として知られているアイスランドですが、世界経済フォーラムによる世界のジェンダー・ギャップ指数ランキングによると、15年連続世界1位を記録しています。つまり、長年「世界で最も男女平等な国」であり続けています。(日本は2024年度の同調査によると、146か国中118位。)講演はアイスランドの紹介に始まり、再生可能エネルギー、男女平等社会実現等について詳しく説明していただきました。社会を変えるには、他者に頼るのではなく、自ら変えようとする姿勢が重要という強いメッセージをいただきました。
(司会生徒感想①)
駐日アイスランド大使講演会

講演会後、高1国際進学クラスの数名が、クラスで発行する英字新聞用に大使にインタビューをさせていただきました。また、夏休み中にアイスランド大使館を訪問し、「アイスランド」を特集した記事を書く予定です。
日本から約8,500キロ離れているアイスランドですが、今回の講演会を機に、少し距離が近くなった気がします。多摩市と「友好協力関係」にあるアイスランド。毎年6月17日の独立記念日に、アイスランドを身近に感じられるとよいですね。
生徒の感想
当日は学生会館を満たす程の人数で、上手く司会役が務まるのかと心配がありましたが、ステファン大使が気さくに話しかけてくださり、緊張も和らぎました。ご講演の内容も私にとってすごく新鮮なものばかりで、アイスランドについてもっと知りたくなりました。貴重なお時間をありがとうございました。
(司会生徒感想②)
今までよく知らなかったアイスランドについて学ぶことが出来たとともに、ジェンダー平等とはなんなのか、改めて考える良い機会になりました。実は今回、私が読ませていただいた原稿の中に、アイスランド語が含まれていたのですが、事前挨拶の際にアイスランド大使の方に発音を確認していただいたところ「まるでネイティブのようだ」と褒められたことがとても嬉しかったです。おかげで本番でも、緊張せず職務を全うすることができました。もしまたアイスランドに関するイベントなどがありましたら、ぜひ参加させていただきたいと思います。
7月6日に「おやじの会」の総会が行われました。発足以来最大規模の参加数となり、会員数も年々増加しております。一部では、日本最大級ではないかとささやかれているようです。おやじも学校の行事に参加しようと始まった会ではありますが、昨今、学校の教育活動や広報活動にも参画していただいています。そんな中、日頃からテニスを趣味にしている方同士で、テニスをしようということになりました。いつも学校イベントに協力していただいている「おやじの会」の皆様に感謝も込めて、学校のテニスコートを提供しました。教員も数名交じり、爽やかな汗を流し、交流を深めました。「今度は、テニス部部員も含めて試合がしたい。ここは俺たちのウインブルドンだ!」と、意気込みを語る「おやじの会」テニスメンバーたちでした(^^♪
おやじの会(テニスイベント)

今回は、学校HPに掲載したものの一部を再編集し『多摩の風』に掲載しています。記事をまとめていて、どれを取り上げたらいいかとても迷ってしまいました。様々なイベントが開催されていて、大妻多摩のコンテンツの充実ぶりを実感しました。外部の方からすると、施設の充実ばかりが注目されがちですが、それに負けないくらいの教育プログラム、それを支えるスタッフ(教員だけでなく保護者も!)充実していると私は思います。生徒の皆さんも、この恵まれた環境を是非享受してもらいたいと願っています。
編集後記


















